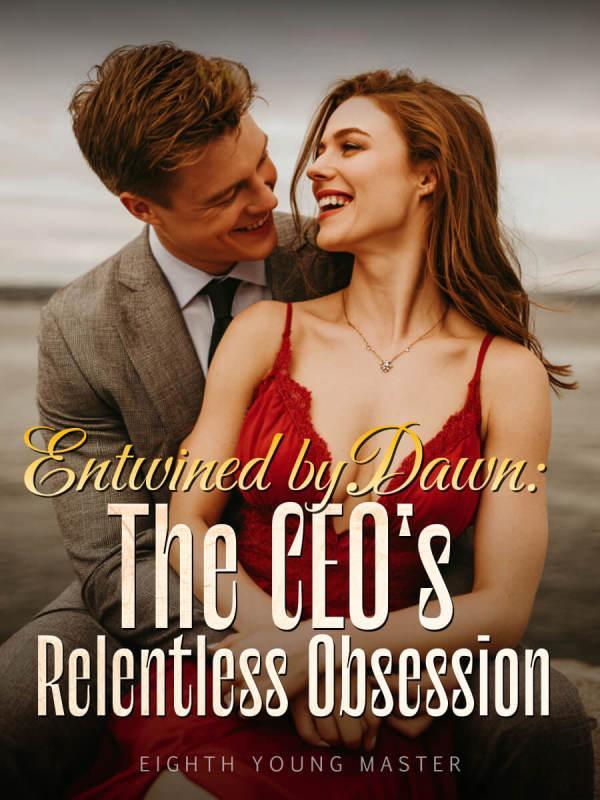©WebNovelPub
Vermillion-Chapter 22.3
Editor: ShinonomeResearchLabs, Proofer: Hakou
腹を鳴らしながら、木の器を片手に、焚き火の周囲に集まる隊商の面々。ケイたちも同様に用意していた器にリゾットをついでもらって、テントの傍の木の下で食べ始める。
The members of the caravan gathered around the bonfire with rumbling stomachs, wooden bowls in hand, waiting for their turn to get the risotto. Having gotten their share, Kei and Aileen sat down and started eating under a large tree near their tent.
「しかしアレだな、たまに単語が通じないもんだな」
“You know, I think some words just can’t be conveyed in this world.”
もしゃもしゃとリゾットをかき込みながら、アイリーン。当たり前だが、ケイもアイリーンも、今現在話しているのは英語だ。
Complained Irene while absentmindedly stirring her risotto. Of course, both of them are currently speaking English.
「ああ。ゲームの中だと考えもしなかったが、同じ英語といっても、言語として成立の仕方が違うんだろう」
“Yeah, I didn’t think it was like this in the game, but if I say something in English, it gets translated to a different language when we’re talking to the people of this world.” (ED Note: The mechanics for the language are either poorly explained, or I just can’t translate it. Either way, sorry for the confusion at this part: it’s best if you don’t think too much about it as it’s mostly for context.)
頷いて答えたケイに、アイリーンは自前のサラミを齧りつつ、ふむと一息ついて首を傾げた。
To Kei’s reply, Aileen simply took a large bite out of her salami and exhaled, throwing her head back in resignation.
「『トラウマ』って、ラテン語起源だっけ?」
“Is ‘trauma’ derived from Latin?”
「いや、たしかギリシア語だったと思う。ゲーム内に、ギリシア語圏はなかったからな……多分ギリシア語そのものが存在しないんじゃないか」
“No, I think it was Greek. However, there were no Greek-speaking groups in the game… it’s likely the Greek language as a whole doesn’t exist in this world.”
【DEMONDAL】は、北欧のデベロッパが開発したゲームであり、運営会社はイギリス資本であった。プレイヤー人口の八割以上はヨーロッパ圏の住人だったため、ゲームの主言語は英語に設定されていたが、それと同時に雪原の民ロスキ、高原の民フランセ、海原の民エスパニャなど、幾つかのヨーロッパ言語に対応したエリア・民族も実装されていたのだ。
Demondal was developed by a scandinavian company, but operated from a server in Britain. Since more than 80% of the player base was composed of European residents, the main language of the game was set to English. Nonetheless, several European languages were assigned to different groups in-game: Russian to the Snowfield people, French to those from the plateau, and Spanish to the rest living by the sea.
「だけど、旦那らが話すフランス語って、起源を辿ればラテン語だろ。んでもって、ラテン語も元を辿れば、ギリシア語に行きつくんじゃなかったっけ?」
“The French language was derived from Latin, but if we traced back Latin too, wouldn’t it end up as Greek as well?”
「うーむ。『トラウマ』みたいにダイレクトな形じゃないにせよ、英語にもギリシア語起源の語彙は多い筈だからな。こっちの言語がどういう形で成立したのか、言語学的に興味はあるな……」
“Umu, even though most of them are not as direct as ‘trauma,’ there still are a lot of Greek words in english too, but given that it doesn’t exist here, I’m really curious as to how the language in this world was formed… ”
「ウルヴァーンの図書館で、そういうのも調べてみたら、面白いかも知れないぜ?」
“Wouldn’t it be interesting if you looked into that kinda thing at the Uruvan library?”
「時間があったら挑戦してみたいところだ……が、学術的な英語は俺にはちょっと難しいんだよな」
“I’d like to do it if I had the time… but academic English is rather difficult for me.”
器の中身を食べきって、ケイは小さく溜息をついた。
Kei let out a small sigh as he worked away at the contents of his bowl.
ケイは、後天的な英語話者だ。
English was Kei’s second language.
VR技術の黎明期、世界中の似たような境遇の患者たちと交流するために、ケイは比較的幼い頃より、コツコツと英語を学んできた。おかげで、というべきか、普通の日本人の子供よりも遥かに、生きた英語や、その他のヨーロッパ言語に触れる機会があったのだ。英語に限っていえば、日常生活に支障のないレベルで、訛りなどもなく流暢に喋れるようになっている。しかし、基本的に実地での叩き上げによる語学力ゆえに、殆ど縁の無い学術的な英語は苦手としていた。
Kei had been studying English since the dawn of VR technology, when he was relatively young, to be able to talk with other patients with conditions similar to his own. Thanks to VR, he had been exposed to English and other European languages much more than the average Japanese student, so much so that he had been able to pick it up to the point where it was usable in day to day life. Nonetheless, Kei was still blindsided by academic English, as there was no opportunity to use or learn it in his avant garde education in the language.
「俺はバイリンガルじゃないからな……アイリーンが羨ましいよ」
“Since I barely count as bilingual… I’m jealous of Eileen.”
「バイリンガルっつっても、オレも、英語は完璧ってワケじゃないんだぜ?」
“My English isn’t perfect either, you know?”
羨望の眼差しを向けるケイに、照れたような表情で肩をすくめるアイリーン。
Aileen shrugged her shoulders with an embarrassed expression as Kei stared at her enviously.
「あくまで、オレの母語はロシア語だからな……はぁ、ロシア語が懐かしいぜ」
“It’s because my native language is Russian… ha~, I do miss Russian.”
おどけた様子で、わざとらしく、アイリーンは溜息をついて見せる。
Aileen deliberately sighed in an exaggerated manner.
そこに、唐突に。
Then, suddenly.
「――Тогда давай поговорим на русском со мной」
『――In that case, you can speak Russian with me.』(ED Note: I’m going to abuse these weird brackets for any foreign languages in the future, cuz god damn are there a lot.)
背後から投げかけられた言葉。
A voice from behind them offered.
弾かれたように二人は振り返る。
The two turned around as if spun like a top.
「……お前は、」
“… You are―”
ケイは、言葉を呑みこんだ。
Kei swallowed his words.
そこにいたのは、薄く笑みを浮かべて、木の幹に寄りかかった金髪の男。
A blond man leaned against a nearby tree trunk while sporting a thin smile.
――昼下がり、馬車の修理の際に見かけた、あの青年だった。
――It was the young man that Kei met while he was helping repair the carriage in the afternoon.
「Ты говоришь на русском языке!?」
『You speak Russian!?』
驚きの表情で、アイリーンが問いかける。
Aileen blurted out in surprise.
「Да, я русский」
『Yes, I’m Russian in fact.』
したり顔で頷く青年。アイリーンはさらに、
The young man nodded as he confirmed Aileen’s suspicions, who continued,
「Я удивлена! Я не дубала, что есть русский в этом караване」
『What a surprise! I’d never have thought that there’d a fellow Russian on this caravan.』
「Ага, но это правда. Меня зовут Алексей, а Ты?」
『Yeah, me neither, but it’s true. My name’s Alexei, and you?』
「Меня зовут Эйлин」
『My name’s Aileen.』
「Эйлин? звучит по-английски」
『Ai-lean? That how you pronounce it in English?』
「Именно так. Это потому, что мои родители англичане…」
『Precisely. Both my parents are English, you see… 』
喜色満面で、ロシア語会話を繰り広げるアイリーンと青年。
Aileen and the young man happily chatted away in Russian.
「…………」
“ … ”
ひとり、取り残されたケイは、その顔に紛れもなく困惑の表情を浮かべていた。
Kei, having been left out, had an unmistakably puzzled expression on his face.
「――っと、すまん、ケイ、」
“――Oops, I’m sorry Kei.”
ほどなく、ケイが置いてけぼりを食らっているのに気付き、アイリーンが英語に戻す。
Noticing Kei had quietly slipped away to finish his meal, Aileen returned to speaking English.
「いやいや、その……、驚いたな。雪原の民なのか」
“No, no, don’t mind me. It’s just that… I was surprised. Are you one of the Snowfield people?”
ぎこちなく笑みを浮かべながら、ケイは金髪の青年を見やった。
While giving an awkward smile, Kei addressed the blonde youth.
「ああそうだ。あんたとは、昼にはもう会ったよな」
“Oh, that’s right. I met you earlier today.”
ニヤッ、と口の端を釣り上げて、青年はケイに手を差し出す。
Smirking, the young man extended his hand to Kei.
「よろしく、おれの名前はアレクセイ。雪原の民の戦士だ」
“Nice to meet you, my name’s Alexei: a warrior of the Snowfield people.”
「……俺は、ケイという。よろしく頼む」
“… I’m Kei. Nice to meet you too.”
ぐっ、とアレクセイの手を握り、簡単に自己紹介を済ませる。アレクセイは、かなり握力が強かった。
Kei took Alexei’s hand and introduced himself. He noted to himself that Alexei had a very firm grip.
「アレクセイも、護衛なのか?」
“Is Alexei also an escort?”
「いや、おれは戦士だが、護衛として雇われてはいない。ただ、ピエールの旦那とは個人的な知り合いでな、ウルヴァーンまで馬車に乗せて貰えることになったのさ」
“No, I am a warrior, but I wasn’t hired as an escort. Rather, I’m an acquaintance of Mr. Pierre. I tagged along because I was planning on heading to Uruvan as well.”
「そうか、なるほど……」
“Ah, I see… ”
曖昧に頷きつつ、ケイは次の話題を探そうとする。しかし、それよりも早く、アレクセイがアイリーンに向き直った。
Giving a vague reply, Kei desperately grasped for the next topic, but before he managed to find one, Alexei turned to Aileen again.
「Но я был удивлен, потому что я никогда не думал, что такая красивая девушка находится здесь」
『But I’m surprised. I never thought I’d find such a beautiful girl here.』
「…Хватит шутить」
『… Don’t joke around.』
「Я серьезно. На самом деле удивительно」
『I’m serious. You’re really amazing.』
再び始まる、異言語の応酬。流れるような会話に、口を挟む余地は感じられない。楽しげに話す二人をただただ眺めながら、ケイは無言のまま、顔に愛想笑いのようなものを張り付けていた。
And, the foreign language dialogue continued, leaving no room for a third party. While the two conversed, Kei simply looked on silently, a twitching smile plastered to his face.
「おーいケイ、ちょっといいか」
“Oi~, Kei, are you free right now?”
と、その時、焚き火の向こう側から、ダグマルがケイを呼んだ。
Dagmar called out from across the bonfire on the other side of the clearing.
「すまんが、今日の夜番と仕事の件で話がある。ちょっと来てくれ」
“Sorry to bother you, but we’re gonna have a talk about today’s work and plan the night watch, so can you come here for a sec?”
「あ、ああ、分かった」
“Ah, I understand.”
上司の呼出とあっては仕方ない、ケイはやおら立ち上がる。そして、迷ったように視線を揺らして、アイリーンの方を向いた。
As it couldn’t be helped since it was in boss calling, Kei stood up to go. As he was about to leave, a lost expression crept back onto his face as he nervously turned towards Aileen.
「――それじゃあ、ちょっと行ってくる」
“――So then, excuse me, I’ll be going for a moment.”
「Честно говоря, Я не принадлежу к… あ、うん。Я не принадлежу к никакому клану в этом регионе….」
『Honestly, I don’t belong to… ‘Oh, yeah, sure.’ Like I was saying, I’m not from any clan in this region… 』(ED Note: Words in single quotation mark spoken in English to Kei.)
ちら、とケイを見やり、しかしアレクセイとの会話を継続するアイリーン。
Aileen briefly glanced at Kei and replied before turning back to her conversation with Alexei.
ケイは、一瞬だけ――アレクセイが、面白がるような表情を向けてきた気がした。
Kei thought he saw an amused expression cross Alexei’s face momentarily.
「…………」
“ … ”
何とも言えない、疎外感のようなもの。
Kei couldn’t quite put his finger on the feeling that he was having, but it was something like alienation.
それを、ぐっと、腹の奥底に追いやって、ケイは二人に背を向けた。
As he turned away from the pair chatting away, Kei felt like his stomach was aching.
†††
ぱちぱちと爆ぜる焚き火の明かりを、エッダはつまらなさそうな顔で眺める。
Edda looked at the light of the bonfire with a face that practically screamed of boredom.
「…………」
“ … ”
ちら、と焚き火の向こう側に目をやった。
She glanced towards the opposite side of the camp.
小さな木の下で、親しげに語り合うひと組の男女。
Two men and a woman were talking to each other under a small tree.
アイリーンと、アレクセイ。
Aileen and Alexei.
「……魔法、見せてくれるって言ったのに」
“You said you’d show me magic… ”
ちぇ、と唇を尖らせる。実は先ほどからエッダは、魔法が披露される時間を待っているのだが、アイリーンたちの話が一向に終わる気配を見せない。
Edda pouted in annoyance. She had been waiting to see magic the whole evening, but Aileen’s conversation never seemed to end.
直接頼みに行こうか……とは思うものの、アイリーンと話している革鎧の青年が、どうにも恐ろしく感じられた。顔つきのせいか、雰囲気のせいか。あるいは――どうやら彼が、雪原の民であるらしいためか。
She thought of going directly to her… but the young man in the leather armor talking to Aileen was scary. Did he seem that way because of his face or the atmosphere? Or perhaps it was because he was one of the Snowfield people.
(でも、お姉ちゃんは、別に怖くないもんな)
(But, onee-chan isn’t scary.) (ED Note: Internal dialogue syntax reverted to parenthesis: fixed in earlier chapters.)
雪原の民の言葉を、流暢に話すアイリーン。それでも彼女には、『優しいお姉さん』という印象しか抱かなかった。
Aileen spoke the language of the Snowfield people fluently. Still, Edda still thought of her as a friendly big sister.
だが、その相手の男は、何だか怖い。粗野な獣というか、そんな雰囲気を感じる。
Nevertheless, the other man was still frightening. He gave off the feeling of a wild beast.
(……もう一人のお兄ちゃんは、怖くないのにな)
(… I’m not scared of the other onii-chan either.)
昼からアイリーンとずっと一緒に居た黒髪の青年は、まだ優しい瞳をしていたのに、と。
The dark-haired young man who had been with Aileen this afternoon had gentle eyes.
しかし、その黒髪の青年も、今はテントの中にいる。
However, the young man with black hair was now back in his tent.
先ほどダグマルと話しているのを小耳に挟んだが、彼は今晩、遅くに夜番を担当するらしい。それに備えて、早目に睡眠を取るとのことだった。
From his exchange earlier with Dagmar, he seemed to have a night watch shift, and in preparation, he said he was going to sleep early.
寝る前にアイリーンに挨拶をするも、あまり相手にしてもらえず、すごすごと寂しげにテントに入っていく様は、まるで餌を取り損ねて巣穴に戻る熊のようだった。
Edda wanted to talk to Aileen before going to bed, but wanted to avoid the scary young man. In the end, she felt like a bear running back to its burrow after losing its food.
(お兄ちゃんとお姉ちゃんは、どういう『関係』なんだろう?)
(What kinda relationship does onii-chan and onee-chan have?)
ふと、エッダはそんなことを考えた。
That thought suddenly slipped into Edda’s mind.
――「友達」なのか。
――Are they friends?
――あるいは、「恋人」なのか。
――Or maybe they’re lovers?
ただの友達にしては親しげだったわ、とエッダはにらむ。ませた興味と、純粋な好奇心のままに、エッダは二人の仲を夢想する。
“They seemed too close to be called friends,” Edda thought. With her pure, childish curiosity Edda fantasized about the pair’s relationship.
「……うーん」
“… Unnn.”
首を傾げて空を見上げるも、そうしている間に眠気が襲ってきて、最終的には「ま、いいや」と軽く流した。
Edda tilted her head up and looked up at the sky. As Edda gazed as the stars, she was hit by a wave of drowsiness, which she adamantly brush off with a “well, whatever.”
「……エッダや。そろそろ、おねむかい?」
“… Edda, are you going to sleep?”
ふわり、と暖かいものに包まれる。
Something warm gently wrapped itself around her.
「……おばあちゃん」
“Grandma… ”
振り返るまでもなく、分かる。だぼだぼのローブ、皺だらけの細い腕、ふんわりとしたお日様の残り香。背後から、ハイデマリーに抱き締められているのだ。
Edda didn’t need to look back to tell who was hugging her. A baggy robe, arms as thin as sticks, and a soft, lingering scent: it was Heidemarie.
「まだ、眠くないもん」
“I’m not sleepy yet.”
「ふぇっふぇ、そうかいそうかい」
“Fufufu. Alright, alright.”
「ふぇっふぇ、そうかい」
強がるエッダに、ハイデマリーは、ただ小さく笑った。
Hugging Edda tighter, Heidemarie simply let out a small laugh.
「……ねえ、おばあちゃん」
“… Hey, grandma.”
「ううん?」
“Uun?
「雪原の民っていうけど、『雪原』ってどんなところなの?」
“Where the Snowfield people are from, Yukihara: what’s it like?”
「……そうだねぇ」
“… Ah, Yukihara?”
膝の上に座るエッダの髪を撫でながら、ハイデマリーはしばし考える。
Heidemarie thought for a moment while stroking Edda’s hair as she was sitting on her lap.
「雪原は、”公都”ウルヴァーンよりさらに北、国境を超えた『北の大地』に広がる地域で、山々に囲まれた険しい土地じゃよ。まあ、とてもとても、寒いところじゃ。夏は涼しいが、冬は長く、厳しい。そこに住まう人々、雪原の民は、その環境にも負けない強い人々と聞く」
“Yukihara is the region stretching north from the outpost city Uruvan, beyond our country’s border, and is a barren land surrounded by mountains. The winters are long and harsh, and the people who live there, the Snowfield people, are a fierce tribe that have learned to withstand the demanding environment.”
「へぇ。でもなんで、その人たちは、そんな寒いところに住んでるの?」
“Hey, but why do they live in such cold places?”
「遥かな太古の時代には、緑豊かな土地であったとか……何故、今も住み続けているか、といえば、やはり先祖から受け継いできた土地だから、かのう」
“In ancient times, it was a fertile land… I suppose the reason they continue to live there today is because they inherited it from their ancestors.”
「ふぅん」
“Fuun… ”
「……ああ。それに、彼らの使う秘術も関係するかもしれん」
“… Ah, in addition, it could also be because of their mystic arts.” (ED Joke: “I-it’s a secret family technique!!”)
「ひじゅつ?」
“Mystic arts?”
「――『紋章』、と呼ばれておる。多大な命の危険を代償に、獣の魂をその身に宿し、人とは思えぬような力を発揮する業、らしいんじゃが。詳しいことは、わたしも知らないよ」
“――It’s called ‘Crest Arts.’ At the peril of one’s life, the technique allows a person to manifest powers that are impossible for a normal person, though even I don’t know the details.”
「魔法みたいなものなのかな」
“Is it magic?”
エッダの独り言のような問いに、ハイデマリーは小さく唸る。
In response to Edda’s barrage of questions, Heidemarie spoke in a hushed voice.
「雪原の民の一族でも、限られた人間しか使えぬそうじゃ。ただし、その使い手に『紋章』を贈られた戦士は、普通の戦士とは比べ物にならないほどに強くなる、ということだけは確かじゃの」
Even in the clans of the Snowfield people, only a limited number of people know how to use it. However, a warrior who has attained a Crest is incomparably stronger compared to a normal warrior. That’s the only thing I’m sure of.”
「知ってるの?」
“How do you know?”
「昔、のぅ。一度だけ、『紋章』を刻まれたという、雪原の民の戦士に会ったことがある。それはそれは、鬼神の如き強さじゃった。『北の大地』には、そんな戦士がごろごろいるんだとか」
“A long time ago, I once met a warrior of the Snowfield people how had a Crest engraved on him. That warrior was as strong as a demon. There are people like that in Yukihara.”
ハイデマリーの言葉に、エッダは目を輝かせた。
Edda’s eyes shined hearing Heidemarie’s story.
「すごいなー、行ってみたい」
“Wow, I want to go there!”
「ふぇっふぇ、それは少し、危ないかもしれんのぅ」
“Fuwehehe, that might be a little dangerous.”
指でエッダの巻き毛をとかすようにして、ハイデマリーはゆっくりと頭を撫でる。
Heidemarie slowly stroked Edda’s head, combing through the girl’s long, curly hair with her fingers.
「かの”戦役”より昔、その『紋章』の秘術を巡って、公国は雪原の民に戦争を仕掛けたんじゃ。今では、”戦役”のせいで、公国内では殆ど忘れられておるがの。殴った側はすっかり忘れても、殴られた側はその痛みを忘れない――かの地では未だに、公国に対する深い恨みが残っていると聞く」
“The Principality went to war with the Snowfield people in order to obtain the secret ‘Crest Arts.’ Nowadays, it’s almost entirely forgotten by the public. However, enough one side forgot, the side who suffered the attack won’t do the same so easily. I hear that there’s still a deep grudge against the Principality in that place.”
「そう、なんだ」
“Oh… ”
曖昧に頷いたエッダは、
Interjected Edda blankly,
「……むずかしいね」
“… It’s hard to go to Yukihara, isn’t it?”
ぽつりと、小さく呟いた。
She muttered in a small voice.
「そうだね、エッダには、少し難しいかもしれん。みんな、大人のすることじゃよ」
“Yes, it might be a little difficult for Edda. Even adults have trouble.”
「……じゃあ、わたしも、大人になったらするの?」
“… Then, do you think I’ll be able to do it when I grow up?”
「ふぇっふぇっふぇ。それは、エッダ次第だねぇ」
“Fuwehehe. Well, that depends on you, Edda.”
頭を撫でられる心地よさに、身を任せたエッダは、ふぁ、と小さくあくびをする。
Edda, who resigned herself to having her head comforting stroked, yawned a little.
「さあさ、エッダや。夜はもう遅い……そろそろお眠りなさい」
“Now, now, Edda. The hour is late… it’s time to go to sleep.”
「……まだ眠くないもん」
“… I’m not sleepy yet.”
「ふぇっふぇ、そうかい」
“Fufufu, is that so?”
ハイデマリーは、ただ小さく笑った。
Heidemarie let out a small laugh.
夜は暖かく、深く、全てを包みゆく。その闇の中に、おだやかな眠りを誘い、
The warm, vivid night slowly wrapped its arms around everything, its mollifying darkness gently drawing to a close the curtain of sleep.
しずかに、ゆったりと、すぎていった。
Silently, peacefully, twilight slipped by, giving way to the dawn of a new day.
![Read The Royal Military Academy's Impostor Owns a Dungeon [BL]](http://static.novelbuddy.com/images/the-royal-military-academys-impostor-owns-a-dungeon-bl.png)